“町のサービス業”を応援します
街の小さなお店が、
AIでこんなふうに変わりました
小さなお店のぷちDXと販売促進
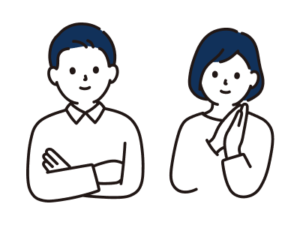
宿・飲食店・商店ほか サービス業 向け
宿・飲食店・商店ほか サービス業 向け
/
主なサービス ①データ分析 → ②販促サポート
①データ分析
成果につながるか手がかりを見つける
メニュー
- Webレポート
※データ集計/分析・専用サービス設定・お打合せによるご説明 含む
※毎月 PDF形式でメール
※お客さま専用のオリジナルダッシュボード作成(LookerStudo)
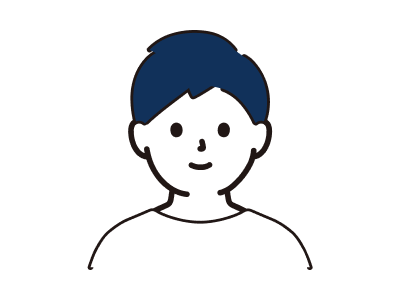
データを見るのが苦手な方もご安心ください。Webレポートをもとに、成果の手がかりをわかりやすくご説明します
②販売促進サポート
事業やお店の魅力を伝える
メニュー
- アイデア出し
- 文章作成サポート
(記事代行作成など) - 撮影サポート
- Instagram運用サポート
- LINE運用サポート
- Googleビジネスプロフィール(Googleマップ)運用サポート
- Web広告
- Webサービス導入サポート
(予約システムなど) - Webサイトおまかせ作業
(作業代行) - Webサイト保守/制作
(制作はWordPress か Stuido 推奨)
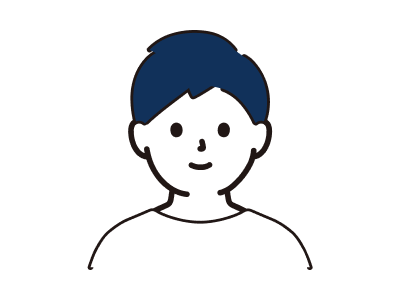
全部ではなくて、地方のサービス業にとって、とくに重要な対応に絞ってサポートしています
支援実績
主に町のサービス業を応援しています
こんな悩みをよく聞きます
町の経営者さまから、こんな悩みをよく聞きます

経営者
そもそも、SNSやホームページがよくわかりません
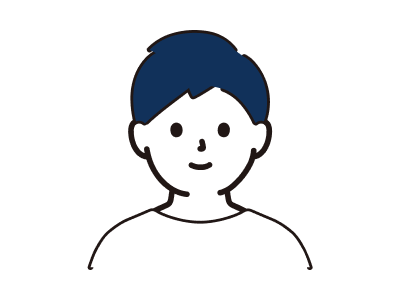
わたしたち
地道な努力を続ければ成果の出る事例も増えています
お悩み 例
- SNSやホームページが大切と実感しているが、時間やお金を十分にかけられないし、そもそもあまりよくわからない
- 制作会社やデザイナーに頼んで作ったホームページはあるが、成果があったのか不明
- SNSやブログを自社で対応しフォロワーも増えていたが、事業の利益が落ち込んでいて、どうすれば改善できるか悩んでいる
・・・そのため、事業の利益を増やせるよう、データ分析を活用した総合的なWebサポートを行っています。少しずつですが成果も出ています
成果 例
- インターネット予約 0→月150件以上
- ホームページ訪問数UP 3年で5.6倍
- 自社予約率 10%増
- 電話対応 80%減
- 企画記事 重要キーワード Google検索順位 1位獲得
あまり人手や予算をかけられない場合がほとんどです
1ヶ月で利益UPとか、即効性の高い魔法のような施策はありませんが、2.3年以上かけてじっくり成果を出す事例がも増えています
わたしたちに協力できそうなことがあれば、WebフォームかLINEにてご相談ください